わんちゃんにとって、なぜ定期的な健康診断が必要なのでしょうか。
彼らは不調を言葉で伝えられず、本能的に隠してしまう我慢強い動物だからです。飼い主さんが異変に気づいた時には、病気が進行していることも少なくありません。
この記事では、犬の健康診断が不可欠な3つの理由、病気の早期発見・早期治療につなげるための具体的な検査内容(血液検査、エコー検査など)、そして成犬期やシニア期といった年齢別の推奨頻度について詳しく解説します。
大切な家族の健康を先回りして守るためのヒントをご紹介していますので、ぜひこの機会に確認してみてください。
なぜ健康診断が必要か

毎日元気そうにご飯を食べて、しっぽを振っているわが子を見ると、「うちの子は元気だから、健康診断なんて必要なのかな?」と不思議に思う方もいらっしゃるかもしれません。
でも、わんちゃんには、私たち人間とは違う、健康診断がとても大切な理由が3つあるんです。
まず、一番大きな理由は、犬は話せないということです。
「なんだかお腹が痛い」「最近少しだるい」といった小さな不調を、言葉で私たちに伝えることができません。
飼い主さんが普段の様子から気づいてあげられることには限界があります。だからこそ、健康診断という客観的なデータが、彼らの体の中の状態を知るための重要な手がかりになるんですね。
次に、わんちゃんはとても我慢強い動物だということ。これは、野生時代の本能で、群れの中で弱みを見せると外敵に狙われてしまうため、不調を隠す習性があるからなんです。
もともと症状が出にくい動物ですが、それに加えて我慢してしまうので、飼い主さんの目から見て「食欲がない」「ぐったりしている」といった明らかな病気のサインに気づいた時には、病気がかなり進行してしまっているケースが本当に多いんです。
そして3つ目は、わんちゃんの加齢スピードは、私たちの想像以上に早いということです。犬の1年は、人間の4年から7年分にあたると言われています。
もし私たちが「1年に1回」の検診を怠ってしまったら、わんちゃんにとっては「4年〜7年」も体のチェックをしないのと同じこと。
その間に病気がゆっくりと進行しても、気づいてあげるのが難しくなってしまいます。
元気そうに見えても、体の中では私たちが気づかない小さな変化が起きているかもしれません。
早期発見・早期治療は、わんちゃんがこの先も長く元気に過ごすための、飼い主さんから贈ることができる最高のプレゼントです!
私たちが先回りして、大切な家族の健康を守ってあげましょうね。
健康診断で何をするのか
獣医師による問診、身体検査

いざ健康診断!となっても、具体的に何をするのか、わんちゃんが怖がらないか、少しドキドキしてしまいますよね。
健康診断は、まず獣医師の先生による問診からスタートすることが多いです。
これは、飼い主さんだからこそ知っている、愛犬の普段の様子を先生に伝える、とても大切な時間です。
わんちゃんは言葉で不調を伝えられないので、毎日の食欲や元気の様子、お散歩での歩き方、おしっこやうんちの回数や状態、お水を飲む量の変化など、飼い主さんが気づいたささいなことを、ぜひ詳しくお話しください。
それが病気のサインを見つける大きなヒントになるんです!
問診が終わると、次は身体検査です。ここでは先生が、わが子の体を隅々までチェックしてくれます。
まずは体重測定や体温測定。それから、目や耳の中、お口の中の歯周病のチェック、皮膚の状態や毛並みを見る視診。
そして、お腹やリンパ節、体を優しく触ってしこりや痛みがないか調べる触診。最後に聴診器をあてて、心臓の音や呼吸音、お腹の動きを聴く聴診をします。
他にも関節の動きなども見てくれますよ。 普段の歯磨きやブラッシングで気になったことや、飼い主さんが不安に思っていることを相談する絶好の機会でもあります。
痛みは伴わない基本的なチェックが中心なので、わんちゃんも飼い主さんもリラックスして受けてくださいね。
血液検査で体内の状態を確認

先生の身体検査が終わったら、次は血液検査に進むことが多いです。私たち人間と同じで、少しだけ採血をして血液を調べる検査です。
なぜこれが必要かというと、外見や触診だけではわからない、体の中の内臓の機能を客観的な数字で確認できる、とっても大事な検査だからです。
検査には大きく分けて2種類あります。一つは血球計算といって、赤血球や白血球の数を調べます。
これで、わんちゃんが貧血になっていないか、体のどこかに炎症が起きていないか、といったことがわかります。
もう一つは血液化学検査です。こちらは、肝臓の数値や腎臓の数値、血糖値、タンパク質など、たくさんの項目をチェックできます。
これらの数値から、肝臓や腎臓がしっかり働いているか、体に栄養が足りているかなど、目に見えない健康状態を知ることができます。
わずかな採血量でこれだけ多くの情報がわかるのは、すごいことですよね。病気の早期発見はもちろんですが、元気な時の数値を知っておくことが、その子だけの健康の基準になるんです。
わんちゃんの血液検査について、もっと詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください↓
【犬の血液検査ガイド】愛犬の元気を守る血液検査の重要性と、検査項目の意味
尿検査、便検査でわかること

血液検査とあわせて、おしっこやうんちの検査もとても大切です。
毎日何気なくお世話で見ているものですが、詳しく調べると、たくさんの健康情報が隠されています。
尿検査では、尿タンパクや尿潜血などをチェックします。これで、膀胱炎や尿石症のサイン、さらには腎臓病の初期の変化や糖尿病の手がかりも見つけることができるんです。
泌尿器系のトラブルは、わんちゃんも辛いもののため、早めに見つけてあげたいですよね。
一方、便検査では、食べたものの消化状態がわかりますし、目には見えない寄生虫の卵がいないか、潜血便なども確認します。
特に寄生虫は、わんちゃん自身のお腹の調子だけでなく、お散歩仲間のわんちゃんや、場合によっては私たち人間にも影響することがあるので、定期的なチェックはとても重要です。
これらの検査は、病院で採尿・採便することもできますが、当日の朝に自宅で採った新鮮なものを検体持参していただくと、わんちゃんのストレスも少なくてスムーズですよ。
エコー検査で臓器の大きさ、動きを確認

健康診断では、エコー検査(超音波検査)を勧められることもあります。これは、体にゼリーを塗って、機械をそっと当てるだけの、痛みを伴わない検査です。
エコー検査のすごいところは、お腹の中や胸の中の臓器の内部構造や形、大きさをリアルタイムの映像で見られることです。
よく聞くレントゲン検査は骨や全体の形を見るのが得意ですが、エコー検査は腹部エコーとして肝臓や腎臓、消化管、膀胱といったお腹の臓器の中身を詳しく見るのに適しています。
また、心臓エコーでは、心臓の動きや血液の流れ方を動画で確認することができるんです。
血液検査の数値が少し高かったり、先生が触診で「あれ?」と思ったりした時に、このエコー検査で詳しく調べます。
目に見えないしこりや、膀胱の結石なども見つけやすいんですよ!検査をする時は、毛が邪魔にならないようにお腹や胸の毛を少し刈らせてもらうことがあります。
また、じっとしてもらう必要があるので、看護師さんや飼い主さんで優しく体を支えてあげながら行います。わんちゃんへの負担が少ない、とても役立つ検査です。
画像診断についての詳細は、こちらの記事から確認してみてください↓
【犬の画像診断ガイド】 犬のレントゲンとエコー検査の役割、画像検査でわかること
《年齢別》健康診断の推奨頻度
子犬期

わんちゃんをお迎えしたばかりの子犬期、いわゆるパピー期は、お家に慣れてもらったり、トイレを教えたり、飼い主さんも大忙しの時期ですよね。
この時期は、混合ワクチンプログラムや寄生虫駆除のために、動物病院に何度か通うことになると思います。
実は、このワクチン接種で病院へ行く機会が、子犬にとっての初めての健康チェックになっているんです。
健康診断とあらためて構える必要はなくて、ワクチンを打ちに来たついでに、先生が体中をしっかりチェックしてくれているんです。
この時期のチェックで大切なのは、元気に成長しているかの確認と、生まれつき体に異常、例えば心臓や関節などに問題がないかを見てもらうことです。
そして、このパピー期にもう一つ大切な目的があります。それは、動物病院に慣れること。
わんちゃんにとって、病院が「注射をされる嫌な場所」ではなく、「先生や看護師さんに優しく触ってもらえる場所」だと覚えてもらうことは、社会化のトレーニングとしてとても重要です。
この時期に病院やスタッフさんに慣れておけば、大きくなってからの健康診断やもしもの治療の時も、ストレスがずっと少なくなりますよ!
成犬期

1歳~6歳くらいまでの成犬期は、わんちゃんが一番元気いっぱいで、体力も有り余っているように見える時期ですよね。
「毎日あんなに走り回ってるんだから、健康診断はまだ早いかな?」なんて思ってしまう飼い主さんも多いかもしれません。
でも、実はこの「元気に見える」成犬期にこそ、年1回の定期検診を受けてほしい大切な理由があるんです。
わんちゃんは本能的に不調を隠してしまうので、飼い主さんが気づかないところでゆっくりと変化が始まっていることもあるんですよ。
そして、この時期の健康診断には病気の早期発見と同じくらい、もう一つとっても重要な役割があります。
それは、わが子の健康の基準値を知っておくことです。元気いっぱいな今の血液検査の数値や、内臓の状態を記録として残しておく。
そうすることで、将来シニア期を迎えたときに、いつもの数値と比べて、どう変化したかを比較するための、かけがえのない基準になるんです。
また、犬種によってかかりやすい病気もあるため、その子の特性に合わせたチェックを始める良いタイミングでもあります。
「まだ若いから大丈夫」と思わずに、未来の健康を守るためのお守りとして、年1回のチェックを習慣にしてあげてくださいね。
シニア期

わんちゃんも7歳以上になると、いよいよ老犬の仲間入りです。見た目はまだまだ元気そうでも、加齢とともに体の中は少しずつ変化してきます。
この時期は、シニア犬に多い病気、例えば心臓病、腎臓病、腫瘍、関節炎などのリスクが、どうしても高くなってきてしまうんですね。
だからこそ、シニア期は健康診断の重要性がぐっと高まります。
もしわが子が7歳を迎えたら、これまでの年1回からステップアップして、半年に1回、つまり年2回の定期検診を受けていただくのが理想です。
シニア期のわんちゃんにとっての半年は、私たち人間にとっては2年〜3年も間隔が空くのと同じ感覚なんです。
その間に、体調が大きく変わってしまうことも少なくありません。
こまめなチェックで目に見えない変化を早く見つけてあげられれば、治療の選択肢も広がりますし、何よりわんちゃんの生活の質を高く保ったまま、穏やかに過ごせる時間を長くすることにつながります。
年齢に合わせて、心臓や腫瘍のチェックのためにエコー検査などを追加することも多いですね。大切な家族と長く過ごすための、前向きな備えとして考えてあげてくださいね。
受診のタイミング

年に1回、あるいはシニア期は半年に1回が良いとわかっていても、「じゃあ、具体的にいつ行けばいいのかな?」と迷ってしまいますよね。
わんちゃんの健康診断を受ける受診のタイミングとして、おすすめの時期や、忘れにくい決め方があります!
一番シンプルで続けやすいのは、わが子の誕生日や、おうちに迎えた記念日を健康診断の日と決めてしまう方法です。
これなら毎年忘れずにスケジュールを組めますよね。 そして特におすすめしたいのが春のフィラリア検査のタイミングです。
だいたい4月から6月頃、フィラリア予防のお薬を始める前には、血液検査が必要になります。
この時に、健康診断の血液検査も一緒にお願いしてしまえば、わんちゃんがちょっと苦手な採血1回で両方の検査を済ませることができます。
これは、わんちゃんの負担も減らせて、飼い主さんにとっても効率的なので、ぜひ検討してみてください!
また、動物病院によっては、比較的空いている秋や冬の時期などに、健康診断キャンペーンを行っていることもあります。
普段よりお得に詳しい検査が受けられることもあるので、かかりつけの病院のお知らせをチェックしてみるのも賢い方法です。
いつが良いか迷ったら、まずはかかりつけの動物病院に相談してみましょう。きっとその子に合ったプランを提案してくれますよ。
思い立ったら吉日!まずは予約のお電話をしてみませんか。
健康診断を受けるメリット
病気の早期発見・早期治療に繋がる

健康診断を受ける一番大きなメリットは、なんと言っても病気の早期発見・早期治療につながることです。
わんちゃんはとても我慢強い動物で、本能的に自分の弱さや不調を隠そうとするので、飼い主さんが明らかな病気のサインに気づいた時には、残念ながら病気がかなり進行してしまっている…というケースが本当に多いんです。
特に、シニア期に増えてくる心臓病や腎臓病などは、初期の段階ではほとんど症状として表に出てきません。
でも、定期的に健康診断を受けていれば、症状が出る前の未病の段階や、ごくわずかな体の中の変化を、血液検査やエコー検査といった客観的なデータでキャッチできる可能性がぐんと高まるんですよ。
もし早い段階で病気を見つけてあげられたら、すぐに早期治療を始めることができます。それは、わんちゃんの体にかかる負担や、辛い思いをずっと少なくしてあげられるということです。
それに、治療の選択肢が広がったり、病気の進行をゆっくりにできる場合も多く、わんちゃんが快適に過ごせる時間を長く保つことにつながります。
結果として、将来的にかかる治療費の負担を抑えることにも繋がるんです。
手遅れになる前に私たちが気づいてあげること、そして早く見つければ、できることがたくさんあるという安心感を得られることこそが、健康診断の最大のメリットなんですね。
うちの子の健康基準がわかる

健康診断には、病気の早期発見のほかにも、もう一つとっても大切なメリットがあります。それは、わが子の健康基準がわかるということです。
血液検査などの結果を見ると、一般的な基準値や正常範囲というものが示されます。
でも、わんちゃんも私たち人間と同じで、犬種や年齢、もともとの体質によって、健康な状態の数値には大きな個体差があるんです。
もしかしたら、一般的な基準値から少しだけ外れているのが、その子にとっては一番元気な状態ということもあるかもしれません。
だからこそ、元気な時から毎年、データ蓄積をしておくことがとても重要なんです。これは、他のわんちゃんと比べるためではなく、過去のわが子と比べるための大切な記録。
まさにうちの子だけの健康カルテを作っていくイメージですね。この、その子独自の健康な時の数値のことを、専門的にはベースラインと呼びます。
このベースラインがわかっていると、将来シニア期を迎えて体調が変化した時、とても役立つんです。
たとえ検査数値が一般的な正常範囲の中におさまっていたとしても、「うちの子のいつもの数値(ベースライン)と比べると、ちょっと上がってきているな」という、本当にごくわずかな病気の兆候に、獣医さんと飼い主さんがいち早く気づいてあげることができるんです!
このデータ蓄積こそが、わが子の生涯を通じた健康管理の、何よりもしっかりとした土台になってくれるんですね。
費用と準備
費用の目安
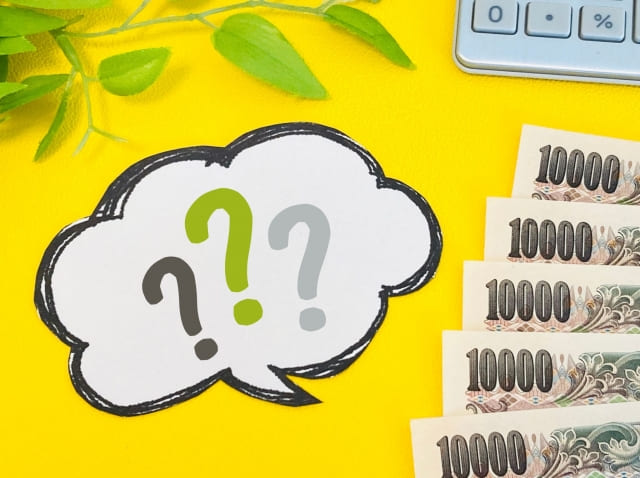
わんちゃんの健康診断が大切だとわかっていても、費用も気になりますよね。健康診断にはいったい、どれくらい準備しておけば良いのでしょうか。
まず大切なこととして、わんちゃんの医療は自由診療が基本となり、私たち人間の健康保険のような保険適用外になります。
そのため、健康診断の費用や設定されているプランは、動物病院によって異なります。
あくまで目安としてですが、問診や身体検査、血液検査、尿・便検査といった基本的な検査項目がセットになったプランの相場は、だいたい1万円から3万円くらいを考えておくと良いかもしれません。
もちろん、地域や病院の規模によっても差があります。
オプションとして、シニア期に受けたいエコー検査やレントゲン検査、ホルモン検査などを追加する場合は、その分の費用が加算されていきます。
安いものではありませんが、これはわが子の未来の元気のための投資だと考えてみてください。
早期発見できれば、将来的な大きな手術や長期の治療を防ぐことにつながり、結果としてトータルの医療費を抑えられる可能性もあります。
ちなみに、ペット保険に加入されている場合、健康診断そのものは保険適用外となることが多いです。
でも、もしその診断で見つかった病気の治療が始まった場合、その治療費は保険の対象になることがほとんどです。
まずはかかりつけの病院に「うちの子に合ったプランだと、目安はどれくらいですか?」と気軽に相談してみるのが一番確実ですね!
当日の流れと準備

健康診断の日が近づくと、飼い主さんもわんちゃんも少しソワソワしちゃうかもしれません。
当日の流れをスムーズにするため、また正確な検査をするために、いくつか準備しておきたいことがあります。
まず、当日の流れをスムーズにするために、事前に予約をしておくことをおすすめします。その際に、当日の注意事項を必ず確認しておきましょう。
病院によっては、事前に問診票を渡されることもあるかもしれません。準備として一番大切なのが絶食です。
血液検査や超音波検査の正確なデータをとるために、獣医師の指示に従って、検査の数時間前からごはんやおやつを抜く必要があります。
これは、胃の中を正確に見たり、食後に血糖値や中性脂肪の数値が上がってしまうと、正しい結果がわからなくなってしまうからなんです。
お水は飲んでも大丈夫なことが多いですが、これも必ず先生の指示に従いましょう。 もう一つの準備が、おしっこやうんちの準備です。
もし当日の朝に新鮮なものが自宅で採れそうな場合は、それを持っていくと検査がとてもスムーズです。
もし難しそうなら、無理せず病院で採ってもらうこともできるか相談してみましょう。
そのほかの持ち物としては、わんちゃんが少しでもリラックスできるように、いつも使っているお気に入りのおもちゃやタオル、キャリーケースなどがあると良いですね。
病院に着いてからの当日の流れは、まず受付をして、問診があります。そのあと、身体検査や採血、お預かりした尿や便の検査、エコー検査など、予約したプランの検査に進みます。
検査結果は、当日わかる範囲で説明してもらえることもありますし、詳しい項目は後日改めて説明を聞きに行く場合もありますよ。
まとめ

わんちゃんは不調を隠す我慢強い動物であり、人間の何倍ものスピードで歳をとります。
元気に見えても、定期的な健康診断は病気の早期発見・早期治療と、その子だけの健康基準(ベースライン)を知るために不可欠です。
血液検査やエコー検査などで体の変化を客観的に把握し、成犬は年1回、シニア期(7歳~)は年2回を目安に受診しましょう!
大切な家族の健康な時間を長く守るため、定期検診を習慣にすることが飼い主さんからの最高のプレゼントになります。
![[初回限定]お試しBOX ¥500(税込)](https://coco.cdn-bp.com/assets/rebranding/images/top/banner_trial01_pc_rn_new.png?var=1673856807758)








































