ライフステージ別の睡眠時間
成犬の睡眠時間の特徴

わんちゃんとの暮らしの中で、すやすやと眠る姿を見ていると、こちらまで幸せな気持ちになりますよね。わんちゃんは一体一日にどれくらい眠るものなのでしょうか。
一般的に、成犬は一日のうち約12時間から14時間を睡眠に費やすと言われています。これは人間と比べるとかなり長い時間ですが、犬にとっては心と体を健康に保つために必要な時間なのです。
ただ、この時間はあくまで目安であり、すべてのわんちゃんに当てはまるわけではありません。犬種や性格によって差のあるものです。
また、その日の過ごし方によっても必要な睡眠時間は変わってきます。ドッグランで思いっきり走り回ったり、新しい場所へお散歩に出かけたりと、たくさんの刺激を受けた日は、いつもよりぐったりと長く眠ることがあるでしょう。
これは、体だけでなく頭も使って疲れた証拠。このように、年齢や犬種、そして日々の運動や活動量に応じて、必要な睡眠時間は柔軟に変動するものだと理解してあげることが大切です。
そして、わんちゃんが安心して眠るためには、心穏やかに過ごせる環境が何よりも重要です。愛犬が安心して深く眠れる静かな環境を整えてあげることが、飼い主さんの大切な役割のひとつです。
愛犬が毎日を元気に、そしてご機嫌に過ごすためには、十分な休息が不可欠です。日中は愛情を込めて遊びや散歩に付き合い、適度な運動をさせてあげること。
そして夜は、家族のそばで安心して眠れる場所を提供してあげること。このような規則正しい生活の積み重ねが、愛犬の健やかな睡眠と、ひいては心と体の健康を育んでいくのです。
老犬の睡眠時間と健康管理

愛犬がシニア期を迎え、一日の中で眠っている時間が長くなったと感じることは、多くの飼い主さんが経験することだと思います。
その穏やかな寝顔は愛おしいものですが、同時に「こんなに寝ていて大丈夫かしら」「どこか具合が悪いのではないか」と、少し心配な気持ちになることもありますよね。
シニア期に入ったわんちゃんは、一日に16時間から18時間、時にはそれ以上眠ることが一般的です。これは成犬期と比べるとかなり長く、子犬の頃と同じくらいの睡眠時間に戻っていくようなイメージです。
体力が少しずつ落ちてきて、日中のわずかな活動でも疲れやすくなるため、体を回復させ、エネルギーを蓄えるためにより多くの休息が必要になるのです。
愛犬が自分の体の声に耳を傾け、今の自分に必要な休息をきちんと取っている証拠でもあるのです。
しかし、私たち飼い主が注意深く見てあげたいのは、その睡眠の質とパターンの変化です。老犬の睡眠は、単なる休息時間を超えて、心と体の健康状態を映し出す大切なバロメーターになります。
例えば、いつもはぐっすり眠っているのに、最近なんだか眠りが浅く、小さな物音ですぐに目を覚ましてしまう。
夜中に何度も起き出して、落ち着きなく部屋をうろうろする。あるいは、今まで見たことのないような寝方をしていたり、いびきが急に大きくなったり、寝ている時に苦しそうな呼吸をしたりする。
こうした変化は、何かしらの不調を知らせるサインである可能性が隠れています。
特に気をつけたいのが、体の痛みが原因で熟睡できていないケースです。例えば関節炎を抱えている子は、同じ姿勢で長く寝ていると関節が痛むため、楽な姿勢を探して夜中に何度も寝返りをうったり、起き上がったりします。
愛犬の寝方をよく確認して、特定の体をかばうような姿勢で寝ていないか、起き上がるときに辛そうな素振りを見せないかなど、日頃のケアの中で優しく観察してあげることが大切です。
このように、睡眠時間の長さだけでなく、その中身をしっかり見てあげることが、シニア犬の健康管理には不可欠です。
日々の暮らしの中で、「いつもと違うな」と感じる小さな変化に気づくためには、普段から愛犬の様子をよく見ておくことが何よりも大切になります。
今日は何時間くらい寝ているかな、どんな体勢で寝ているかな、呼吸は穏やかかな、といった愛情のこもった確認が、病気の早期発見につながります。
そして、何か気になることがあれば決して自己判断せずに、信頼できる動物病院で相談しましょう。
定期的な健康診断は、シニア犬との穏やかな暮らしを続けるためのお守りのようなものです。獣医師さんに愛犬の睡眠の様子を具体的に伝えることも、的確な診断の助けになります。
愛犬が毎日を穏やかに眠るためには、快適な環境を整えてあげることも私たちの重要な役割です。
ささいなことのように思えるかもしれませんが、こうした細やかなケアが、愛犬の睡眠の質を高め、健やかな毎日を支えることに繋がるのです。
愛おしい家族の一員である愛犬が、最期の瞬間まで心地よく、幸せな時間を過ごせるように、私たちにできる限りのサポートをしてあげたいですね。
老犬の睡眠時間が長くなる理由とは?
犬の生理的な必要性

愛犬の一日の中で眠っている時間がどんどん長くなっていく。その姿に、「昔はあんなに活発だったのに」と少し寂しさを感じつつも、穏やかな寝息を立てる様子に愛おしさを感じる飼い主さんは多いのではないでしょうか。
シニア期に入ったわんちゃんの睡眠時間が長くなるのには、ちゃんとした生理的な理由があります。
まず、私たち人間と犬とでは、睡眠の取り方に根本的な違いがあることを理解しておくと、愛犬の長い睡眠時間を受け入れやすくなるかもしれません。
人間は、夜にまとまった時間ぐっすりと眠ることで心身の疲れを取りますが、犬はもともと、浅い眠りと深い眠りを繰り返しながら、一日のうちに何度も短い睡眠を取るスタイルが基本です。
そのため、合計の睡眠時間は長くなりますが、熟睡している時間は意外と短いのです。この基本的な性質に加えて、老化という大きな変化が訪れることで、さらに長い睡眠が必要になってくるのです。
その最大の理由のひとつが基礎代謝の低下です。老化に伴い、何もしなくても消費されるエネルギーである基礎代謝は少しずつ落ちていきます。
これは、体を動かすためのエネルギーを作り出す効率が悪くなることを意味します。シニアになるとエネルギーの消耗が激しくなり、回復にも時間がかかるようになります。
例えば、お客様が来て興奮したりするだけでも、体力を大きく消耗してしまいます。その消耗した体力を回復させ、次の活動に備えてエネルギーを再び蓄えるためには、身体を休ませる時間、睡眠時間を長く取ることが絶対に必要になるのです。
また、睡眠は単に体を休ませるだけのものではありません。眠っている間に、体の中では細胞の修復や再生、そして免疫機能の維持といった、生命を維持するための大切な働きが行われています。
特に、年を重ねた体は、日々の生活の中で少しずつ細胞が傷ついたり、機能が衰えたりしがちです。そのダメージを一つひとつ丁寧に修復し、病気に対する抵抗力を保つためには、若い頃よりも長いメンテナンス時間が必要となります。
愛犬がすやすやと眠っている時間は、いわば自分の体を一生懸命メンテナンスしている最中なのです。
さらに、脳の健康を保つ上でも睡眠は極めて重要な役割を果たします。日中に経験した様々な出来事や学習したことを記憶として定着させたり、脳の中に溜まった老廃物を掃除したりする作業は、主に睡眠中に行われると言われています。
また、老化による腎機能の低下などで夜中にトイレに起きる回数が増えることもあります。そうすると、夜間にまとまった睡眠が取りにくくなるため、その分を日中のうたた寝で補おうとします。これも、体が必要な睡眠時間を確保しようとするための、自然な調整機能なのです。
このように、老犬の睡眠時間が長くなる背景には、エネルギーの消耗を抑え、体を修復し、脳を休ませるという、いくつもの切実な生理的理由が隠されています。
それは、変化していく自分の体と向き合い、一日一日を大切に生きるための、わんちゃんなりの知恵であり、生命力そのものだと言えるでしょう。
環境要因が影響する睡眠

愛犬がシニア期を迎え、長くなった睡眠時間を健やかで穏やかなものにしてあげるために、生理的な変化への理解と共に、私たち飼い主が積極的に整えてあげられるのが生活環境です。
若い頃はどんな場所でもへそ天でぐっすり眠れた子も、年を重ねるにつれて、周りの環境に対してとても繊細になります。愛犬が心から安心して体を休められるかどうかは、この環境づくりにかかっていると言っても過言ではありません。
まず、最も基本的なことは、静かで落ち着ける寝場所を確保してあげることです。シニアになると聴覚が衰えてくる子も多いですが、その一方で、予期せぬ物音に対しては以前より敏感に反応し、驚いて起きてしまうことがあります。
家族の気配が感じられるリビングの隅など、落ち着けるけれど孤立しない場所を選んであげるのが理想的です。
その子の性格による個体差も大きいので、どこで寝ている時が一番リラックスしているか、日頃の行動をよく観察して最適な場所を見つけてあげましょう。
次に、温湿度管理も非常に重要なポイントです。犬は人間よりも体温調節が苦手で、特にシニアになるとその機能はさらに低下します。
暑い夏は熱中症のリスクが高まりますし、寒さや足元からの冷えは関節の痛みを悪化させる原因にもなりかねません。
夏場はエアコンで部屋全体を快適な温度に保ち、クールマットを敷いてあげるなどの工夫を。冬場は、すきま風が入らない場所にベッドを置き、肌触りの良い暖かい毛布を用意してあげるなど、季節に合わせた配慮が不可欠です。
そして、愛犬が毎日使うベッドそのものにも、愛情を込めてこだわってあげたいところです。体が沈み込みすぎず、硬すぎない、体圧を分散してくれるような素材のベッドは、弱ってくる関節や筋肉への負担を和らげてくれます。
また、シニアになると自力で起き上がるのにも一苦労することがあったり、万が一の粗相に備えて、カバーが外せて洗いやすい素材であると、衛生的に保つことができ、飼い主さんのケアの負担も軽減されます。
こうした物理的な環境だけでなく、心理的な環境も愛犬の睡眠に大きな影響を与えます。犬は家族の感情の変化にとても敏感な動物です。
常にピリピリとした空気が流れていたりすると、犬は強いストレスや不安を感じ、リラックスして眠ることができなくなってしまいます。
また、大きな生活の変化も大きなストレスの原因となります。環境の変化に適応するのに時間がかかるため、その間の不安が睡眠の質を低下させてしまうのです。
もし愛犬の睡眠に何か問題、例えば夜中に何度も起きる、落ち着きなくうろうろするといった行動が見られた場合、その原因は身体的な問題だけでなく、生活環境の中に潜むストレスにあるのかもしれません。
穏やかで予測可能な毎日の生活リズムは、シニア犬にとって何よりの安心材料です。私たち飼い主が、愛情を持って穏やかな生活環境を提供してあげることが、愛犬の安らかな眠りと、健やかなシニアライフを守ることに繋がっていくのです。
老犬の睡眠時間が短い理由とは?
老化による身体的変化
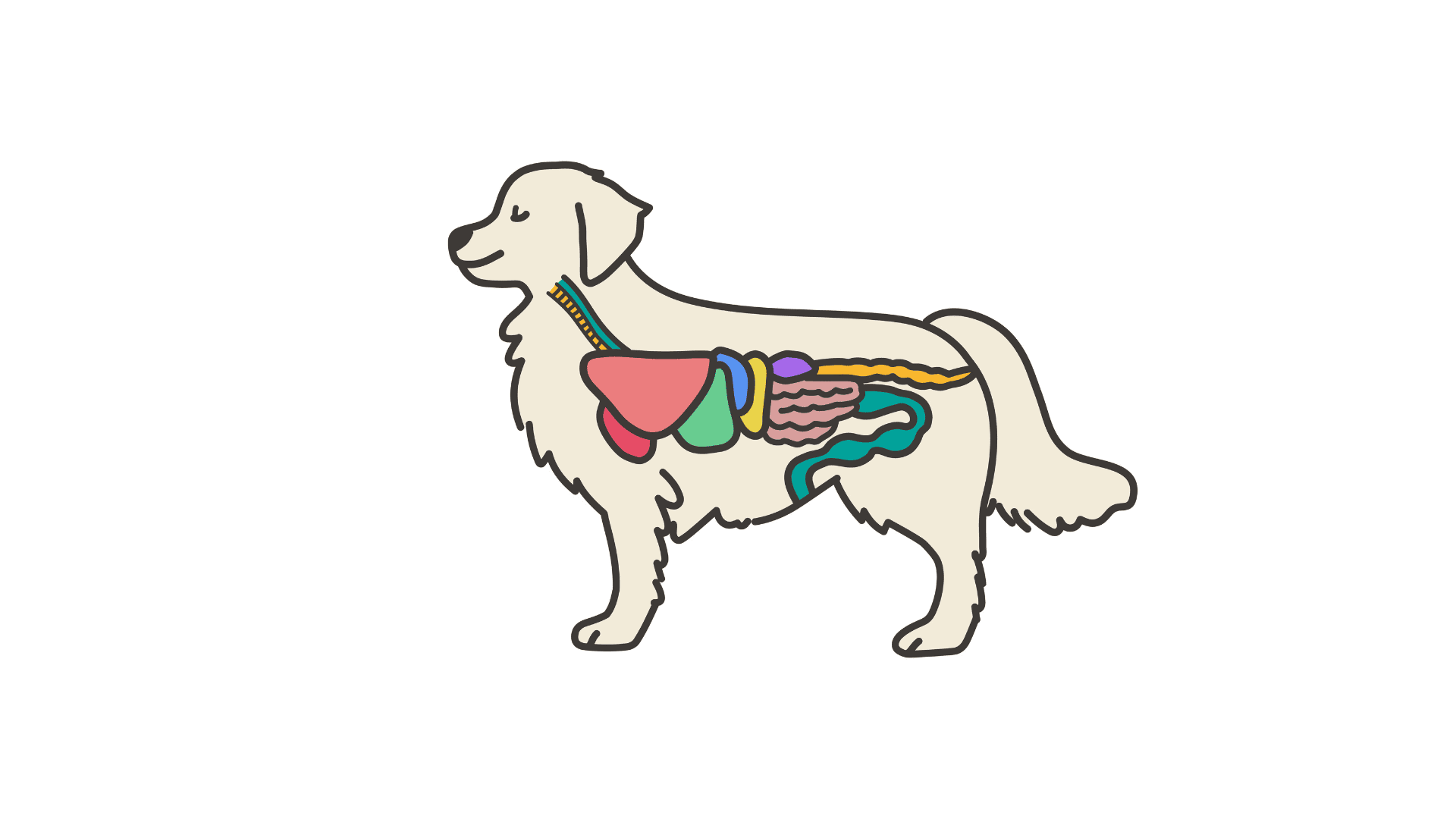
シニア犬は寝てばかりというイメージがある一方で、愛犬が寝ないと心配される飼い主さんの声も少なくありません。
睡眠が長くなる子もいれば、逆に眠りが浅くなり、夜中に何度も目を覚ましてしまう子もいます。その背景には、様々な身体的な変化が隠れていることが多いのです。
眠りたいのに眠れない、その辛いサインを私たち飼い主がきちんと受け止めてあげることがとても大切です。
最も大きな原因として考えられるのが、筋肉や関節の衰えです。高齢になると、人間と同じように犬も筋肉量が低下していきます。
体を支える筋力が弱くなることで、関節にかかる負担は増大し、関節炎などの痛みを抱えやすくなります。
寝る際の体勢を維持すること自体が、実は大きな苦痛になっていることがあるのです。楽な姿勢を探そうと寝返りをうちたくても、体を動かすこと自体に痛みが伴うため、なかなかスムーズに動けない。
その結果、眠りの浅い状態でうとうとしては、痛みで起きてしまう…という辛いサイクルを繰り返してしまいます。これでは、心身の回復に不可欠な深い睡眠を得ることはできません。
愛犬が寝床で何度も体勢を変えたり、起き上がる際に辛そうな素振りを見せたりするようになったら、それは痛みのサインかもしれません。
また、目に見える部分だけでなく、内臓機能の低下も睡眠の質に大きく影響します。特に、腎臓の機能の衰えは、多くのシニア犬が経験する変化です。
腎臓は尿を濃縮する働きを担っていますが、その機能が低下すると、薄い尿がたくさん作られるようになります。
そのため、おしっこの回数が増え、夜間であっても尿意で目を覚ましてしまうのです。わんちゃん自身も粗相はしたくないので、トイレに行きたくて何度も起きる、という行動につながります。
これは、飼い主さんの睡眠不足の原因にもなり得ますが、何よりもわんちゃんの安眠を妨げる深刻な問題です。
さらに、心臓や呼吸器の機能が低下している場合、横になって長く眠る姿勢が苦しく感じられることもあります。
特定の体勢になると咳が出たり、呼吸がしにくくなったりするため、楽な呼吸ができる姿勢を探して、なかなか寝付けない、あるいはすぐに起きてしまうのです。
消化機能の衰えによって、夜間に胃もたれや胸やけのような不快感を覚え、ぐっすり眠れない子もいます。
これらの内臓機能の変化は、外見からは分かりにくいですが、確実に愛犬の体力や快適さを奪っていきます。
そして、忘れてはならないのが、皮膚や体温調節機能の変化です。年齢を重ねると、皮膚は乾燥しやすくなり、かゆみが出たり、床ずれができやすくなったりします。
この絶え間ないかゆみや痛みは、安眠を妨げる大きな原因となり、目が覚めてしまうことも少なくありません。
これらの様々な身体的な衰えは、それぞれが独立しているわけではなく、互いに影響し合って、愛犬から質の良い深い睡眠を奪っていきます。
痛みや不快感で眠れない日々が続けば、体力はますます低下し、体の回復も追いつきません。それは、いずれ必要になるかもしれない介護の段階を早めてしまう可能性もはらんでいます。
愛犬の睡眠の変化は、単なる老化現象として片付けるのではなく、体の内部で起きている問題のサインとして捉え、何ができるかを考えてあげること。
それが、高齢の愛犬に対する私たちの愛情表現であり、大切な役割なのです。
心理的要因とストレス

愛犬の眠りが浅くなったり、夜中に何度も起きたりする原因は、体の痛みや機能の衰えといった身体的な変化だけではありません。
私たち人間と同じように、犬も心を持ち、感情豊かに生きています。特にシニア犬は、心の状態がとても繊細になり、ちょっとしたことが大きなストレスや不安につながることがあります。
そして、その心の揺れ動きが、穏やかな眠りを妨げる大きな原因となってしまうのです。そこで毎日の決まったルーティンが、心の安定を保つための大切な支えとなります。
そのため、引っ越しや大がかりな模様替え、新しいペットを迎えるといった出来事は、私たちが想像する以上に大きなストレスとなります。
自分の縄張りであるはずの家の中が見知らぬものに変わり、安心できる場所が分からなくなってしまう。
そうした強い不安が、常に神経を張り詰めさせた状態を作り出し、リラックスして眠りにつくことを難しくしてしまうのです。
そして、何よりも愛犬の心に深く影響するのが、飼い主さんとの関係性の変化です。犬にとって、飼い主さんは世界のすべてと言っても過言ではありません。
その飼い主さんとのコミュニケーションが、意図せず減ってしまうことも、シニア犬の不安を煽る一因となります。
わんちゃんは、些細な変化を敏感に感じ取り、「自分はもう必要とされていないのではないか」という孤独感を募らせてしまうことがあります。
これらの心理的な問題は、目に見える傷や病気とは違い、周りからは理解されにくいという難しさがあります。
しかし、愛犬が送っているサインを見逃さないでください。睡眠の問題は、彼らが抱えるストレスや不安、悩みを代弁していることがあります。
もし愛犬の様子に気になる変化があれば、まずは獣医師さんに相談してみましょう。認知機能の低下など、医学的なサポートで改善できることもあります。
また、行動学に詳しい専門家に相談することで、愛犬の不安を和らげるための具体的な方法についてアドバイスをもらえるかもしれません。
大切なのは、愛犬の心の状態を理解しようと努めること。そして、今まで以上に愛情深いコミュニケーションを心がけ、愛犬が心から安心できる環境を整えてあげることなのです。
昼夜逆転を改善する方法
生活リズムの見直しと調整

愛犬が夜に眠ってくれず、昼間に寝てばかりいる昼夜逆転の生活は、見ている飼い主さんにとっても、そして何よりわんちゃん自身にとっても辛い状態です。
認知機能の低下などが背景にあることも多く、どうしたら良いのかと悩んでしまいますよね。でも、諦める必要はありません。
根気は必要ですが、日々の生活リズムを丁寧に見直し、少しずつ調整してあげることで、その悩みを軽減し、穏やかな夜を取り戻すための手助けをしてあげることができます。
その鍵となるのが、乱れてしまった体内時計をもう一度整えてあげるという視点です。
私たち人間や犬の体には、約24時間周期で心身の状態を変化させる体内時計という仕組みが備わっています。
この体内時計が正常に働くことで、日中は活動的になり、夜になると自然に眠気を感じるという、健康的な睡眠のサイクルが保たれるのです。
しかし、シニア期に入り、認知機能や体力が低下してくると、この体内時計のリズムが乱れやすくなります。
乱れたリズムを改善し、正しいサイクルへと導いてあげるために、毎日の生活の中に時間の目印をいくつも作ってあげることが非常に重要になります。
最も効果的で、今日からすぐに始められるのが、食事の時間を毎日同じ時間に固定することです。
食事は、わんちゃんにとって一日のうちで最大級の楽しみなイベントであり、生活における非常に強力な目印となります。
朝ごはんを毎朝きっかり7時にあげると決めれば、その時間が一日の活動のスタートの合図となり、体が「朝だ、起きる時間だ」と認識するきっかけになります。
同様に、夜ごはんの時間も毎日定時にすることで、体内時計にリズムを刻み込むことができます。
空腹を感じる時間、消化器官が活発に動く時間が一定になることで、生活リズム全体が整いやすくなるのです。この食事時間のルールは、週末なども含めて毎日必ず守ることが改善への近道です。
次に大切なのが、夜の就寝時間を一定に保つことです。その際には就寝に至るまでの時間を使って、心と体を睡眠モードへと穏やかに切り替えてあげるための入眠儀式を取り入れることをお勧めします。
例えば、夜ごはんの後は、興奮するような遊びは避けて、静かに過ごす時間とします。テレビの音量を少し下げ、部屋の照明も少し暗めに調整するのも良いでしょう。
その後、体をゆっくり撫でてあげたり、穏やかな声で「おやすみ」と話しかけてあげたりします。
こうした一連の流れを毎日繰り返すことで、わんちゃんは「これが終わったら、安心して眠る時間なんだ」と学習し、自然な眠りに入りやすくなります。
まず、一日の流れを思い浮かべてみましょう。まるで時間割の一覧を作るように、朝起きる時間、ごはんの時間、お散歩の時間、そして夜寝る時間、というように、生活の柱となる時間を決めてあげるのです。
この決まった日課を毎日繰り返すことで、わんちゃんは先の見通しを持つことができ、漠然とした不安が軽減されます。規則正しい生活は、わんちゃんにとって最高の安心材料なのです。
この生活リズムの調整は、改善が見られるまでにはある程度の時間が必要です。しかし、焦らず、愛情を持って根気強く続けていくことが何よりも大切です。
乱れてしまった体内時計の針を、飼い主さんが優しく正しい位置へと導いてあげる。その丁寧な日々の積み重ねが、愛犬の穏やかな睡眠と、ご家族全員の安らかな夜を取り戻すための、最も確実な一歩となるはずです。
乱れてしまった愛犬の生活リズムを整え、穏やかな夜の睡眠を取り戻すためには、毎日の生活にメリハリをつけてあげることが大切です。
適度な運動と日光浴

乱れてしまった愛犬の生活リズムを整え、穏やかな夜の睡眠を取り戻すためには、毎日の生活にメリハリをつけてあげることが大切です。
そのための具体的なアプローチとして、適度な運動と日光浴はとても効果的な方法です。シニア期のわんちゃんにとって、これらは大きな意味を持っています。
無理のない範囲で、愛情を込めて日々の生活に取り入れてあげましょう。日光浴に関して、朝、太陽の光を浴びると、脳内でセロトニンという神経伝達物質が分泌されやすくなります。
このセロトニンは、気分を安定させ、幸福感をもたらしてくれる働きがあり、このセロトニンは、夜になると睡眠ホルモンであるメラトニンに変化し、自然な眠りを誘ってくれるのです。
シニア犬にとって、長時間の散歩は体力的に難しいかもしれません。しかし天気の良い日に、窓際にお気に入りのベッドを置いてあげたり、ベランダで一緒にひなたぼっこをしたりするだけでも、その効果は十分に期待できます。
毎日15分以上の日光浴を行うことは、愛犬の健康維持に役立つと言われています。日光を浴びることで、皮膚でビタミンDの生成が促されると考えられているからです。
日中に外の光と空気に触れる習慣は、「今は活動する時間だよ」と体に教え込み、昼夜の区別をはっきりとさせるための優しく、そして確実な方法なのです。
そして、もう一つの大切な柱が適度な運動です。シニア犬にとっての運動の目的は、体力を消耗させることではなく、心地よい疲労感を得て、心と体をリフレッシュさせることにあります。
過度な運動は逆に関節を痛める原因にもなりかねないので、その子の体力やその日の体調をよく観察しながら、無理のない範囲で行うことが大前提です。
例えば、お散歩であれば、愛犬のペースに合わせてゆっくりと歩き、気の向くままに匂いを嗅がせてあげるのがおすすめです。
様々な匂いを嗅ぐ行動は、犬にとって脳を非常に良く使う活動であり、良い刺激となって心を満たしてくれます。
お天気が悪い日や、お散歩が難しい日でも、室内でできることはたくさんあります。おやつを隠して探す遊びも良い刺激になります。
こうした遊びの時間を日中に設けることで、昼間の活動量が増え、夜にぐっすりと眠りやすくなります。
大切なのは、シニアだからと活動を制限しすぎるのではなく、その子の今に合った楽しみを見つけてあげること。
日中に適度な運動や日光浴を取り入れ、心と体を心地よく目覚めさせてあげること。その積み重ねが、夜の穏やかで深い睡眠へとつながり、愛犬のかけがえのない毎日を、より豊かで幸せなものにしてくれるはずです。
![[初回限定]お試しBOX ¥500(税込)](https://coco.cdn-bp.com/assets/rebranding/images/top/banner_trial01_pc_rn_new.png?var=1673856807758)






































