犬用ウェットフードの基礎知識
ウェットフードとは?

ウェットフードとは、その名の通り水分をたっぷり含んだ犬用の食事のことを指します。一般的には75%前後の水分を含み、缶詰やレトルトパウチ、トレーなどの形で販売されていることが多いです。主成分としては、鶏肉や牛肉、魚介類、生肉などの動物性たんぱく質が中心に使われており、素材の風味や見た目を生かした“スープ”タイプ、“ムース”状にしたもの、“パテ”のように滑らかに仕上げたものなど、さまざまな形状があります。
最近では“ナチュラル”志向の飼い主さんの間で、できるだけ無添加で作られたウェットフードや、“シュリンプ&サーモン”などのおしゃれでこだわりのレシピものが人気を集めています。中には“キャットフード”と間違われやすいパッケージデザインのものもあるため、購入時にはよく確認が必要です。
ウェットフードは嗜好性が非常に高いという特徴があります。においや見た目が豊かで、犬にとって「おいしそう」と感じやすいのが魅力です。もともと食が細い子やシニア犬、水分摂取が必要な子にとっては食べやすく、日々の食事に楽しみをプラスしてくれる存在になります。
また、水分量が豊富なことから、自然と水分補給にもつながります。特に夏場や室内の乾燥した時期などは、水を飲む量が減りがちになる犬にとって、ウェットフードはとてもありがたい存在です。食べ物を通じて無理なく水分が摂れるというのは、健康維持にも役立つポイントといえます。
さらに、最近のウェットフードは、栄養バランスにも配慮された商品が多く、たんぱく質やEPA、オメガ脂肪酸などがきちんと含まれているものが増えています。魚介類を使ったものや、グレインフリー(穀物不使用)の商品も選択肢に入ってきており、愛犬の体質や好みに合わせて自由に選べるのも魅力のひとつです。
ただし、総合栄養食として販売されているものと、おかずのように主食のトッピングとして使う“副食”タイプがありますので、パッケージに書かれている内容をしっかり確認することが大切です。毎日のごはんとして使うなら、必ず「総合栄養食」と明記されているものを選びましょう。
ウェットフードは、犬の食事に対して“楽しみ”や“潤い”をプラスしてくれる存在です。素材の良さを活かしたものや、見た目が美味しそうなものなど、選ぶ楽しみも広がるのが魅力です。愛犬の食欲や体調に合わせて、ドライフードと上手に組み合わせて取り入れていくのもおすすめです。
ドライフードとの違い

犬のごはんといえば、日常的に見かける「ドライフード」があります。ウェットフードとドライフード、この2つのフードには水分量や保存性、風味などに大きな違いがあるんです。
まずドライフードは、その名の通りしっかり乾燥されていて、水分含有量はだいたい10%前後ととても少なめです。粒状の形で保存がしやすく、常温で長期間ストックできるというのが大きなメリット。忙しい毎日でも扱いやすく、コスパの良さも魅力のひとつですね。また、ドライフードは噛みごたえがあるため、歯の健康を意識する飼い主さんにも選ばれやすい傾向があります。中には「フリーズドライ」と呼ばれる特殊な製法で作られたタイプもあり、素材の風味をより感じられるものもあります。
一方でウェットフードは、水分量が多くしっとりとした食感が特徴です。お肉やお魚を蒸したような香りが広がり、犬にとってはとても魅力的に感じられるようです。最近では“ポークの煮込み風”や“トマト入りレシピ”など、素材にこだわったレトルトタイプも増えていて、食のバリエーションが広がっています。ただし水分を多く含んでいる分、開封後の保存には注意が必要で、特に夏場などは早めに使い切ることが大切です。
犬用ウェットフードのメリットとデメリット
ウェットフードのメリット

ウェットフードの一番の魅力といえば、なんといってもそのおいしそうな香りと柔らかさ。袋を開けた瞬間に広がる、鶏肉や馬肉、ダック、フィッシュなどの素材本来の風味が、愛犬の食欲をそそるポイントです。香りがしっかり感じられることで、普段から食にあまり興味を示さない子や、高齢で食欲が落ちてきた子にも“食べてみようかな”という気持ちを後押ししてくれることがあります。
また、ウェットフードは肉類をたっぷりと使用している商品が多く、主食としての栄養バランスにも配慮されたものが増えています。例えば、ミネラルやビタミンなどの微量栄養素がバランスよく含まれていたり、レバーなど栄養価の高い部位が使われていたりと、毎日の健康的な食事のひとつとして選ばれることがあるのも納得です。最近ではライフステージや体質に合わせて設計されたレトルトタイプも登場していて、選択肢の幅がぐんと広がっています。
さらに注目すべきなのが、水分をしっかり含んでいるという点です。とろっとした食感やグレービー仕立てのソースで仕上げられているウェットフードは、水分量が全体の70%前後あるものも多く、食事をしながら自然に水分を摂ることができます。特に、日頃から水をあまり飲まない子や、乾燥しやすい季節には、水分摂取を意識するきっかけにもなるかもしれません。
また、食感のやわらかさもウェットフードの大きな利点です。カリカリとしたドライフードに比べてやさしい口当たりのため、歯やあごの力が弱ってきたシニア犬や、まだあまり噛む力がないパピーにも取り入れやすいという特徴があります。中にはミルク仕立てのものや、トロっとしたタイプのものなど、よりやさしく工夫されたレシピもありますので、愛犬の好みに合わせて選ぶ楽しさもありますね。
このようにウェットフードには、香りや食感のよさに加え、栄養面や水分摂取という点でもメリットがたくさんあります。毎日のごはんとしてはもちろん、特別な日のごほうびや体調に合わせた“プラスワン”の食事としても、ウェットタイプは頼りになる存在です。愛犬が元気に過ごせるよう、食事のバリエーションにウェットフードを取り入れてみるのもひとつの方法です。
どちらが良いかというのは、犬の体調やライフスタイルによって異なります。例えば、お水をあまり飲まない子には水分を含んだウェットフードを取り入れることで自然な水分摂取につながることもありますし、食いつきが落ちてきたシニア犬には香りや柔らかさのあるウェットタイプが向いているかもしれません。一方で、運動量が多い若い犬には、カロリーや栄養バランスの調整がしやすいドライフードをベースにし、必要に応じてトッピング的にウェットを加えるなどの工夫もできます。
ドライとウェット、どちらにもそれぞれの利点と欠点があるため、いちばん大切なのは愛犬の様子をしっかり見ながら選ぶことです。時には両方を組み合わせて与えることで、「今日はこっちにしてみようかな」と日々のごはんがちょっとした楽しみにもなります。ペットフードは毎日続くものだからこそ、家族の一員である愛犬にとって無理なく、おいしく、そして健やかに過ごせるような選び方を心がけたいですね。
ウェットフードのデメリット

ウェットフードにはたくさんの魅力がありますが、選ぶ際にはいくつか注意しておきたいポイントもあります。そのひとつが、やはり価格面です。一般的にドライフードと比べると、ウェットフードは内容量に対して価格が高くなりやすく、毎日の食事として取り入れる場合はコストが気になる方もいらっしゃるかもしれません。特に少量ずつパッケージされたペースト状のものや、サーモンや牛肉などの贅沢な食材を使ったタイプ、着色料を使用せず素材にこだわった商品などは、プレミアムな価格帯で販売されていることが多い印象です。
また、保存面に関しても、ウェットフードならではの取り扱いに注意が必要です。缶詰タイプやレトルトパウチのものは、未開封の状態では長期保存が可能な一方で、開封後は冷蔵保存が必要となります。特に水分を多く含んでいるため、空気に触れると傷みやすく、数日以内に使い切るのが理想です。
さらに、食感がやわらかいことは一見良いことのように思えますが、これが歯の健康に影響を及ぼす可能性も指摘されています。ドライフードのようにしっかり噛むことが少ない分、歯石や汚れがたまりやすくなることがあるといわれています。もちろん、ウェットフード自体が直接の原因とは言いきれませんが、やわらかい食事が続くと歯のケアが疎かになりやすいため、飼い主さんが意識してケアしてあげることが大切です。定期的な歯磨きや、デンタルケア用のおやつを取り入れるなど、サポート方法を考えてあげると安心です。
こうしたデメリットを知っておくことで、ウェットフードとの付き合い方がより明確になります。たとえば、メインの食事はドライフードにして、ウェットフードは“ちょっと贅沢なトッピング”として活用する方法もあれば、体調に合わせて時々切り替えるというやり方もあります。大切なのは、それぞれのフードの特徴を理解し、愛犬のライフスタイルや好みに合わせてバランスよく取り入れていくこと。どんな選び方をしても、飼い主さんの気配りがいちばんのごちそうになるのかもしれません。
犬用ウェットフードの選び方
年齢やライフステージに応じた選び方

犬の体は年齢やライフステージによって必要とする栄養が変わっていきます。そのため、ウェットフードを選ぶ際には「子犬用」「アダルト(成犬用)」「高齢犬用」といった表記をしっかり確認し、愛犬の状態に合ったものを選ぶことがとても大切です。
たとえば、生後数か月の子犬は成長期の真っ只中。骨や筋肉、内臓が発達する大切な時期なので、エネルギーやたんぱく質、カルシウムなどをしっかり補えるようなフードが求められます。成長を支える栄養がたっぷり含まれている子犬用のウェットフードは、やわらかくて食べやすいものも多く、初めてのごはんにも取り入れやすいでしょう。
一方で、成犬になると、今度は“体を維持するための栄養バランス”が重要になります。必要以上のカロリーを摂りすぎないよう配慮されている商品も多く、体型管理や日々の活動量に合わせて選べるようになっています。特に運動量が多くない犬や、おうちでのんびり過ごす時間が長い子には、アダルト用の中でもカロリー控えめなものが合うこともあります。
そして高齢犬になってくると、消化吸収のしやすさや関節などのケアが気になる方も増えてきます。最近では“エイジングケア”という視点で開発されたウェットフードもあり、やわらかくて香りがよく、食欲が落ちてきた子にも食べやすいよう工夫されているものが多く見られます。年齢によっては、腎臓への負担を考慮した設計や、噛む力が弱くなった犬のためのペースト状のものなど、細やかな配慮が感じられる商品も増えています。
また、全年齢対応と記載されたウェットフードもありますが、成長期やシニア期など、特定の悩みがある場合には、その時期に合った専用のフードを選ぶほうが安心です。特に持病があったり、体調に変化が出やすい犬の場合は、年齢だけでなく、生活スタイルや健康状態に応じたフードを選ぶことがポイントになります。
どうしても迷ってしまう時は、かかりつけの動物病院に相談してみるのもひとつの方法です。愛犬の好みや体調、年齢などを踏まえて、ぴったりなフードを一緒に探してくれることもあります。種類がたくさんあって迷ってしまいがちですが、だからこそ選べる楽しさもあるはずです。
食材の品質と栄養バランス

ウェットフードを選ぶうえで、どんな食材が使われているかをしっかり確認することはとても大切です。パッケージの裏面に書かれている原材料表示には、そのフードがどんな素材を主成分にしているかが記載されています。たとえば、鶏肉や牛肉、魚などの動物性たんぱく質が最初に表記されていれば、それが主な原料として使用されているということになります。良質なタンパク源がしっかり使われているかどうかが、フードの品質を見るうえでのひとつのポイントです。
最近では、野菜や穀物などの植物性素材をバランスよく配合したウェットフードも増えていて、素材本来の旨味を引き出すような製法で作られているものも見られます。お肉だけでなく、食物繊維やビタミン、ミネラルといった栄養素が含まれていることによって、より総合的な栄養バランスが意識されているフードも選ばれるようになってきました。
犬にとって必要な栄養素は、たんぱく質や脂肪、炭水化物、ビタミン、ミネラルなどがありますが、ウェットフードごとにそのバランスには違いがあります。たとえば、活動量が多い犬にはたんぱく質や脂肪がしっかり含まれているものが好まれる傾向にありますし、シニア犬や運動量が少ない子には、脂肪分をやや抑えたタイプのほうが合う場合もあります。日々の食事を通じて無理なく栄養を摂れるよう、愛犬のライフスタイルや年齢に合わせて選んであげたいですね。
また、人工的な香料や着色料、保存料の使用についても確認しておくと安心です。最近では、ナチュラル志向の飼い主さんを中心に、できるだけ添加物が少なく、素材の風味を生かしたシンプルなレシピを好む傾向も広がっています。特別な体質やアレルギーがある場合は、使用されている原材料を細かくチェックしてから与えるようにするとより安心です。
犬の嗜好や体調、年齢によって「ぴったり」と感じるフードはそれぞれ異なりますが、だからこそ選択肢が多いのは嬉しいことでもあります。ラベルに書かれている栄養成分の数値や使用されている原材料をしっかり確認しながら、愛犬にとって無理のない“毎日のごはん”を見つけていけるといいですね。
ウェットタイプとドライタイプのドッグフードは栄養価がこんなに違う!?
添加物の確認
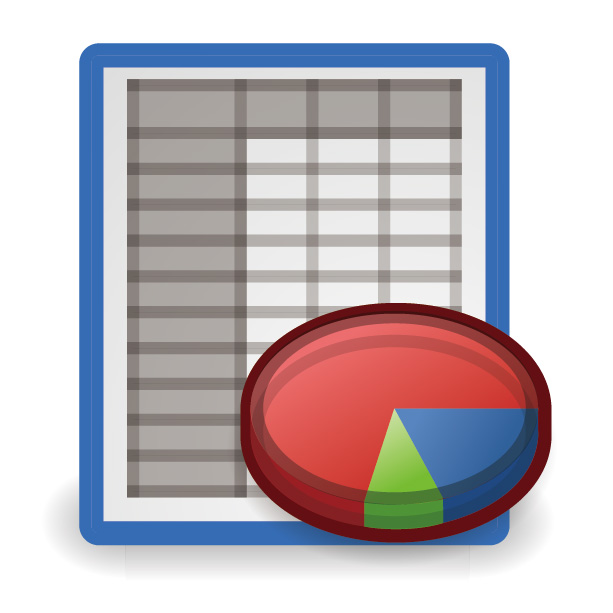
ウェットフードを選ぶ際に意外と見落とされがちなのが、添加物のチェックです。パッケージの表面だけでなく、原材料の詳細が記載されている部分をしっかり確認することが大切です。特に、保存料や着色料、香料などがどのような目的で使われているのかを把握しておくと、より安心して選べるようになります。
最近では「無添加」と表示されているフードも増えてきましたが、その言葉の意味は意外と幅広く、すべての添加物が不使用というわけではないこともあります。たとえば、「合成保存料は使用していません」と書かれていても、別の保存方法や天然由来の成分が使われていることがあります。だからこそ、「何が入っていないのか」「何が代わりに使われているのか」を表示の中から丁寧に読み取ることが、選ぶうえでのポイントになります。
また、着色料にも注目してみてください。見た目の彩りを良くするために使用されていることがありますが、犬にとって色の識別は人ほど重要ではありません。むしろ、味や香りのほうが嗜好に影響するため、見た目の美しさよりも中身の栄養や安全性を重視するのが良いでしょう。
アレルギーを持つ犬の場合は、添加物だけでなく、アレルゲンとなりやすい原材料にも目を向けておく必要があります。たとえば、小麦や大豆、乳製品などが苦手な子もいますし、特定のタンパク質源に反応を示す場合もあります。こうしたアレルギーに配慮されたフードは、パッケージや商品説明に「アレルゲンに配慮」といった案内があることもあるので、参考にしながら選んでみるのもおすすめです。
原材料欄には使用された成分が多い順に表示されているため、最初に書かれている素材ほど割合が多いという目安になります。「保存料」「香料」「着色料」などの表記が後半に小さく記載されていることもありますが、その有無や種類をチェックすることで、安心材料につながることもあります。
添加物がすべて悪いというわけではありませんが、日常的に与えるフードだからこそ、できるだけシンプルな構成で、必要なものだけが適切に使われている商品を選ぶのが理想です。何が入っていて、何が入っていないか。それをきちんと知ることが、愛犬の健康を守る第一歩になるのではないでしょうか。フード選びに迷ったときは、商品ごとの成分表示を丁寧に読み取って、納得できる一品を選びましょう。
犬用ウェットフードの正しい与え方
与える量と頻度

ウェットフードを与えるうえで、まず意識したいのが“適切な量”です。フードのパッケージには、「1日に与える量の目安」が書かれていることが多いですが、これはあくまで一般的な基準です。犬の体重、年齢、活動量によって必要なカロリーは大きく異なるため、愛犬の状態に合わせて調整してあげることが大切です。
たとえば、体重5kgの成犬の場合、1日に必要なウェットフードの量は商品にもよりますが、だいたい150g前後が目安になることがあります。ただし、これはあくまで静かに過ごしている子を基準にした場合です。外でたっぷり運動するのが好きな子や、子犬・成長期にある犬であれば、必要なエネルギー量がぐんと増えることもあります。その場合は与える量を少し多めに調整する必要があります。逆にシニア犬や関節に負担が出やすい体型の子、腎臓などのケアが必要な場合には、カロリーを控えめにしたり、1回あたりの量を調整したりと、細やかな配慮が求められることもあります。
また、フードの“与えやすさ”も考えてあげたいポイントです。たとえば120g入りのレトルトパウチであれば、1回の食事にちょうどよく、開封後も使い切りやすいという利便性があります。毎日のごはんだからこそ、ストレスなく使える量や形状を選ぶことで、飼い主さんの手間も減らせますし、食事の時間が楽しいものになりやすくなります。
基本的には、朝と夜の1日2回に分けて与えるスタイルが多くのご家庭で採用されています。とくに体調の安定が気になる犬や、1回にたくさん食べるのが難しい小型犬などにとっては、定期的に少しずつ与える方が体への負担も少なくて済みます。一方で、食事のたびに催促するような食欲旺盛な子には、1日3回に分けて少量ずつにしたり、おやつの代わりに少し与えるなど、柔軟に対応してあげるのもよいでしょう。
どんなフードであっても、与えすぎには注意が必要です。見た目の満足感や嗜好性だけに頼るのではなく、成分表示やカロリー含有量を参考にしながら、適切な量を見極めていきましょう。定期的に体重をチェックし、必要であればフードの量や種類を交換・調整していくことで、毎日の食事がより愛犬にフィットしたものになります。
他のフードとの併用方法

ウェットフードは単体でも与えることができますが、ドライフードと併用する方法もよく取り入れられています。たとえば、いつものドライフードに少量のウェットフードをトッピングするだけで、食感や香りに変化が出て、愛犬がより食事を楽しめるようになることがあります。とくに食が細くなってきた犬や、食事への興味が薄れている様子が見られる場合には、こうしたちょっとした工夫が役に立つこともあります。
併用する際は、全体のカロリーや栄養バランスを意識することが大切です。ドライフードは総合栄養食として設計されていることが多いですが、そこにウェットタイプを加えると、想定以上のカロリーを摂ってしまうこともあります。とくにパウチタイプのビーフ入りウェットフードなどは、香りや風味がしっかりしていて、つい多く与えたくなってしまいますが、食べすぎには注意が必要です。ドライとウェットの割合を調整しながら、全体で過不足のないように組み合わせてあげると安心です。
また、フードの併用はアレルギーや好みにも配慮しやすいというメリットがあります。たとえば、ある特定のタンパク源(ビーフやチキンなど)にアレルギーがある場合、ドライフードは避けつつ、ウェットフードでは異なるレシピのものを選ぶことで、一部の原材料だけを置き換えるような形も可能です。逆に、好みの差がはっきりしている犬に対しては、好きな風味のウェットフードを一部ブレンドして使うことで、毎日のごはんが楽しい時間になることもあるでしょう。
最近では、ウェットフードを主食ではなく「手作りごはん風」のサイドアイテムのように利用する飼い主さんも増えています。たとえば、ごはんをドライでしっかり整えながら、週末や特別な日にだけウェットタイプをプラスするなど、その活用方法はさまざまです。便利なセット販売のものや、機能に特化したレシピのフードなども出てきており、日々のケアや体調に合わせてフード選びがしやすくなってきました。
何より大切なのは、「その子に合っているか」を見ながら無理なく続けられる方法を見つけることです。いろいろなタイプを組み合わせたり、食事スタイルを見直したりしながら、愛犬とのごはん時間をもっと楽しく、もっと心地よいものにしていきたいですね。
犬のおすすめ総合栄養食を紹介!ウェットフードなど種類別に解説
犬用ウェットフードの保存方法
未開封の保存方法

犬用ウェットフードを購入したら、まず気をつけたいのが保存方法です。未開封の状態でも、保管環境によっては品質に影響が出てしまうことがあるため、適切な場所に保管することが大切です。基本的には、直射日光が当たらず、湿気や高温を避けられる冷暗所に置いておくのが理想です。キッチンの棚や食品ストック用の引き出しなどが、比較的保管しやすい場所としてよく使われています。
特に夏場は気温や湿度が上がりやすいため、エアコンの効いていない部屋や窓際などには置かないようにしましょう。パウチタイプや缶詰タイプなど、包装の形状に関わらず、どれも熱や湿気に弱い性質があります。湿度の高い場所では、外装にカビが生えたり、缶が膨張してしまうこともあるため、注意が必要です。
保存料の入っていないフードや、保存料を極力抑えた“インフリー(添加物フリー)”をうたっている商品も増えてきていますが、そのぶん保存環境にはより気を配る必要があります。安心・安全にフードを保管するためには、温度変化の少ない場所を選ぶことが重要です。とくに自然素材を使った手作り風のタイプは、品質がデリケートな場合も多いため、ラベルに書かれている保存規約などもしっかり確認しておくと安心です。
購入時には、パッケージに記載されている賞味期限も忘れずチェックしましょう。スーパーやネット通販では新旧の在庫が混在していることもあるため、なるべく新しいものを選ぶように意識することで、本来の風味や食感をより良い状態で楽しめます。また、まとめ買いをする際は、フードの消費ペースに合わせて購入量を調整し、古くなる前に使い切れるよう計画的に保管しておくと無駄も防げます。
袋タイプであっても、しっかり密封された状態であれば冷凍する必要はありません。冷凍庫に入れてしまうと、パッケージが結露して中の状態に影響を与えることがあるため、未開封のまま冷凍保存するのは避けたほうが良いでしょう。
フードの種類や形状によって若干の違いはあるものの、どの商品も「保存の基本」は同じです。冷暗所での保管、直射日光の回避、賞味期限の確認。この3つを心がけるだけで、愛犬にとってより良い状態のごはんを用意することができます。
開封後の保存方法

ウェットフードを開封したあとは、できるだけ早く食べきることが理想です。というのも、一度開けたフードは空気に触れることで酸化や劣化が進みやすくなり、時間が経つにつれて風味だけでなく品質にも変化が出てしまう可能性があるからです。とくに酸化防止剤などの添加物をあえて使用していない無添加タイプのフードは、よりデリケートなので保存方法には気をつけたいところです。
開封後は、冷蔵庫での保存が基本になります。パウチタイプや缶詰タイプのフードであっても、パッケージをそのまま冷蔵庫に入れるのではなく、一度密閉できる容器に移し替えておくと、乾燥やにおい移りを防ぎやすくなります。フード専用の保存容器や、小分けにできるガラスやプラスチックの密閉パックなどがあると便利です。冷蔵庫の中では、ほかの食品と一緒に保管することもあるため、しっかりフタが閉まるものを使うと衛生的にも安心です。
保存期間の目安としては、開封後2日以内に使い切ることが推奨されるケースが多いです。これは商品に記載されている保存条件にもよりますが、一般的なかぼちゃやビーフなどの食材を使ったウェットフードは、冷蔵していても時間が経てば風味や食感に変化が出てしまいます。フードのパッケージには「開封後は●日以内に使い切ってください」といった表記があることが多いので、その記載内容を参考にして管理していきましょう。
また、まとめて与えられない場合は、小分け保存という方法もあります。開封後すぐに数回分に分けて容器に入れておき、必要なときだけ取り出せば効率よく使うことができます。とくに50g前後の量であれば、一度に食べきれない子にも調整しやすくなりますし、無駄が少なく済みます。
なお、在庫管理も忘れずに行いましょう。冷蔵庫の奥に入れっぱなしになったまま日数が過ぎてしまうと、見た目では劣化がわかりづらいこともあります。保存した日付を書いたラベルを貼っておくなど、ちょっとしたひと工夫で品質を把握しやすくなります。
愛犬にとって毎日のごはんは体の栄養だけでなく、楽しみのひとつでもあります。おいしい状態のまま食べてもらえるよう、開封後の保存にもぜひ気を配ってみてくださいね。品質の良いフードをより良い状態で保てるように、冷蔵と密閉、早めの使い切りを意識してみましょう。
犬用ウェットフードに関するQ&A
ウェットフードは体に悪いのか

「ウェットフードって体に悪いのでは?」という疑問を持つ飼い主さんも少なくありません。実際には、ウェットフードそのものが体に悪いわけではなく、「どのような原材料を使っているか」や「どのように与えるか」がポイントになります。
まず注目したいのが原材料です。たとえばマグロやチキンなど、動物性タンパク質がしっかり含まれていて、脂質のバランスやビタミン・ミネラルも考慮されているフードは、犬の体づくりにとって有益な栄養を届けてくれます。一方で、犬にとって負担になりやすい成分、たとえば食物アレルギーを引き起こすことがあるグルテンなどを避けた「グルテンフリー」設計の商品もあります。皮膚トラブルや胃腸の不調が出やすい犬の場合には、こういった点もチェックしたいところです。
また、フードの量や与え方も見直してみましょう。たとえば80g〜200g入りのパウチを与える際、犬の体格や活動量に見合った量になっているか確認することが大切です。特に小型犬や高齢犬は消化力が落ちていることもあるため、内臓への負担を考慮して、少量ずつに分けて与えるとよいケースもあります。
「毎日与えてもいいの?」「ドライフードとどっちが体にいいの?」というよくある質問もありますが、ウェットフードは水分を多く含んでいるぶん、自然に水分補給がしやすくなるというメリットもあります。水分摂取量が不足しがちな犬には、こうした面からも役立つことがあります。ただし、水分量が多い分、カロリー密度が低めになる傾向もあるため、総合的な栄養バランスや摂取量には注意が必要です。
DHAなどの成分を含むフードもありますが、機能性を期待する場合は、あくまで「日常の健康維持をサポートする」位置づけで取り入れるのが基本です。病気の予防や治療効果を期待してしまうと薬機法上の表現に抵触するおそれがあるため、あくまで「バランスのよい日常食」という認識で選ぶとよいでしょう。
つまり、ウェットフードが体に悪いかどうかは、選び方と与え方次第です。犬の年齢や体調、アレルギー体質の有無を考慮し、適切な量と頻度で与えることで、ウェットフードは日々の食生活にうまく取り入れることができます。心配なことがあるときは、獣医師に相談しながら選んでいくとより安心です。
食いつきが悪い場合の対策

せっかく選んだウェットフードなのに、愛犬の食いつきが悪くて困っているという声を耳にすることがあります。理由はさまざまですが、ちょっとした工夫で改善することもあるので、いくつかの方法を試してみるのもおすすめです。
まず試していただきたいのが、フードの温度を調整することです。冷蔵庫から出したばかりのウェットフードはひんやりしていて香りも立ちにくく、犬にとっては「食べたい」と感じにくい場合があります。電子レンジで数秒だけ温めて、人肌程度にすることで香りがふわっと広がり、嗜好性が高まることがあります。温めすぎるとやけどの原因になるので、触ってぬるいくらいを目安にしてください。
次に、食材のトッピングを加えてみるのも一つの方法です。たとえば細かく裂いたささみや、蒸したサツマイモなど、犬が好きな食材を少量混ぜてみることで、興味を引いてくれることがあります。ただし、あまりにもトッピングに頼りすぎると、フード本来の栄養バランスが崩れる可能性もあるため、あくまで“ちょっとだけ”が基本です。
また、食事をする環境も見直してみましょう。まわりがにぎやかだったり、落ち着かない場所だったりすると、犬はなかなか集中して食事ができません。食器の場所を少し静かなスペースに移したり、他のペットや家族と少し距離を取ってみるだけでも、気持ちが変わることがあります。安心して食べられる環境を整えることは、意外と大きなポイントになるのです。
さらに、偏食傾向がある子や急に食べなくなった子の場合、消化の不調や下痢などが原因となっているケースもあります。フード自体に問題があるというよりは、体調によって一時的に食欲が落ちているだけかもしれません。そんな時は無理に食べさせようとせず、水分補給を意識しながら様子を見守るのがよいでしょう。状態が続く場合は、動物病院で相談することをおすすめします。
毎日のごはんは、栄養補給だけでなく、犬にとっての楽しみでもあります。「なんで食べてくれないの?」と悩んでしまうこともありますが、少しずつ環境や工夫を変えながら、愛犬にぴったりの“おいしい時間”を見つけていけるといいですね。
![[初回限定]お試しBOX ¥500(税込)](https://coco.cdn-bp.com/assets/rebranding/images/top/banner_trial01_pc_rn_new.png?var=1673856807758)








































